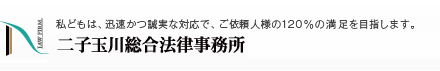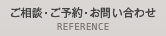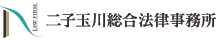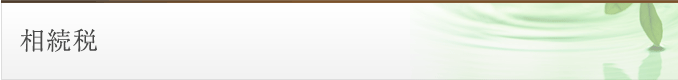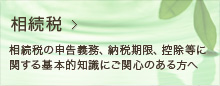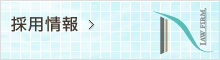1.相続税の申告義務
相続税は、被相続人(お亡くなりになった方)の遺産を相続や遺贈で取得した人に課税されます。
正味の遺産(財産から負債を控除した純資産)の額が、後述する「基礎控除」の額を超える場合に、遺産を取得した者は相続税の申告をする必要があります。申告は、各相続人が協調して一つの申告書として提出することが多いですが、別々に申告書を提出することもできます。正味の遺産が「基礎控除」を超えない場合には、相続税の納税も申告も必要ありません。
2.相続税の申告及び納税の期限
相続税の申告、納税は相続発生後10カ月以内に行う必要があります。
例えば1月20日に死亡した場合、申告・納税の期限はその年の11月20日になります(11月20日に管轄税務署(被相続人の最後の住所を管轄する税務署)に提出、あるいは郵送での提出の場合11月20日の消印で間に合います)。申告と納税はどちらが先でも構いません。
遺言がある場合
遺言書に従って各人が遺産を取得することになり、相続税の申告もそれに基づいて行うことになります。
遺言が無い場合
相続人間で遺産分割協議を行い、遺産分割協議書に調印し、それに基づいて相続税の申告を行います。
相続発生後10カ月以内に遺産分割協議が調わない場合
「未分割」で申告します。未分割の財産は法定相続分通りに分割されたと仮定して相続税計算を行い、各人が納税する必要があります。尚、未分割での申告の場合には、後述の所謂「配偶者控除」や「小規模宅地等の特例」といった税制優遇が受けられません。未分割で申告した場合、その後申告期限から3年以内に遺産分割協議を成立させて財産の取得者が確定した際に、あらためて申告することによってこれらの税制優遇を受けることが出来る場合があります。その場合、当初申告における未分割での申告の時点で、必ず「申告期限後3年以内の分割見込書」という書類を相続税申告書に添付して申告する必要があります。遺産分割が裁判等で争われている等、申告期限後3年以内に分割できないやむを得ない事情がある場合には、申告期限後3年を経過する日の翌日から2ヶ月以内に「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」という書類を所轄税務署長に提出して承認を受けたときは、3年という制限期間を伸長することができます。
3.準確定申告
相続税の申告とは別に、被相続人の所得税の申告書を相続人が提出する必要がある場合があります。
被相続人が給与所得や年金収入だけで、源泉徴収や年末調整で所得税の課税関係が終了している場合は必要ありませんが、事業所得や不動産所得等がある場合、被相続人に代わって相続人が所得税の申告書を提出し、納税します。これを準確定申告といいます。
準確定申告は死亡後4カ月以内に行う必要があります。その年の1月1日から死亡の日までの所得について、準確定申告で申告しますが、前年分の確定申告書を被相続人が提出する前に死亡した場合は、前年分の確定申告書も相続人が提出します。これも死亡後4ヶ月以内にする必要があります。
申告すべき所得がなくて、申告義務が無い場合でも、医療費控除がある場合等は、準確定申告をすることで税金が戻って来ます。還付申告の場合は、4ヶ月を過ぎても還付請求権の時効前(5年以内)であれば、いつでも提出できます。
4.相続税計算の対象
上述の通り、相続税は被相続人の正味の遺産に掛かります。
例えば、資産としては、「不動産(自宅土地建物、貸アパート等)」「金融資産(預貯金、手許現金、株式、投資信託等)」「貸付金(会社への貸付金、家族への貸付金等)」「動産(家財道具、絵画骨董等)」があり、その他に相続財産ではないけれども相続税計算上は相続財産と同等に扱われる「みなし相続財産」として、被相続人が保険料を負担した「生命保険金」(被保険者は被相続人)もあります。(尚、後述するとおり生命保険金の一部は課税対象から除外されます。)これらのプラスの金額を「A」とします。
逆にマイナスの財産としては、「借入金(銀行借入金、知人からの借入金等)」、「未払金(固定資産税の未払金、病院費用の未払金等)」等の債務があります。また、相続人が負担した「葬式費用」も、債務と同様に控除することができます。これらのマイナスの金額を「B」とします。
「A」-「B」が正味の遺産の額となり、これが「基礎控除」を超える場合に相続税申告納税の義務が生じます。それぞれの金額は、被相続人の死亡日現在の価額であり、相続税評価額での評価となり、時価等とは異なる場合があります。
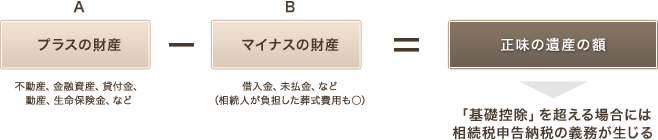
5.基礎控除
基礎控除の金額は、3000万円+法定相続人一人当たり600万円です。(平成27年1月1日以降開始の相続に適用)
正味の遺産の額がこの基礎控除を超える場合に、相続税申告が必要となります。
6.法定相続人
相続税計算に大いに関係してくる法定相続人については、基本的には民法の規定通りですが、一部相続税法独自の規定もあります。配偶者は常に法定相続人となり、子供がいる場合は子供が、子供がいない場合は直系尊属(親や祖父母)が、子供も親等もいない場合は兄弟が法定相続人になります。また、子供が先に死亡していた場合はその子供(被相続人の孫)が相続人となります。(代襲相続と言います)。兄弟が相続人になるべき場合に兄弟が先に死亡していた場合もその子供が代襲相続人になります。
例えば、妻と子供二人(長男と次男)の人が亡くなった場合、法定相続人は3人です。基礎控除の額は、3000万円+600万円×3人=4800万円です。このケースで、次男が既に死亡していて、次男に子供が4人いたとします。そうすると、法定相続人は、妻、長男、次男の子供4名、合計7名になります。この場合には、基礎控除の額は7200万円です。このように、代襲相続の有無により、法定相続人の数が大きく違ってきて、基礎控除の額も変わってくることがあります。
養子も法定相続人ですので、養子縁組をした場合、上記計算に関係してきます。ただし、数多く養子縁組して基礎控除の額を増やすことにより相続税を回避することを防止するために、相続税の計算上法定相続人としてカウントできる養子の数には制限が設けられています。実子がいない場合は2人まで、実子がいる場合は1人のみ養子が法定相続人にカウントできます。
また、配偶者も子もいない状態で、兄弟やその代襲相続人が多く法定相続人の数が多い状態の人が誰かと養子縁組すると、養子は「子供」ですので、子供が法定相続人となる場合は兄弟は法定相続人とはならないため、法定相続人はその養子1人ということになってしまい、基礎控除の額は大きく減少してしまうことになります。このような場合は、相続税上は養子縁組が不利になりますので注意が必要です。
7.相続税の計算
被相続人の「プラスの財産」から「債務や葬式費用」を控除した正味の遺産(「課税価格の合計額」といいます。)が「基礎控除」を超える場合、その超える額(「課税遺産総額」といいます)が相続税の課税対象となります。
相続税の計算は、先ず全体の相続税総額を計算し、その全体の相続税を、各相続人が取得した遺産の価額に応じて案分する形になります。
具体的には、上記「課税遺産総額」を各相続人が法定相続分通りに分割して取得したと仮定します。そしてその各相続人が取得したと仮定した金額を税率表に当てはめて、それぞれの税額を算出します(各人が実際に納税すべき相続税額とは関係ない仮定の数値です)。そのそれぞれ算出した計算額を合計して、全体の相続税を計算します。そして、全体の相続税を各人が取得した正味の遺産(「各人の課税価格」)の割合で案分して、各人の税額を決定します。
| 課税標準 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000万円以下 | 10% | 0 |
| 3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 1億円以下 | 30% | 700万円 |
| 2億円以下 | 40% | 1700万円 |
| 3億円以下 | 45% | 2700万円 |
| 6億円以下 | 50% | 4200万円 |
| 6億円超 | 55% | 7200万円 |
8.法定相続分
配偶者と子供が法定相続人となる場合
配偶者が2分の1、子供が2分の1(子供が複数の場合はそれを等分)となります。
子供がおらず、配偶者と直系尊属が法定相続人となる場合
配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1(直系尊属が複数いる場合はそれを等分)となります。
子供も直系尊属もおらず、兄弟が居る場合
配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1(兄弟姉妹が複数いる場合はそれを等分)となります。
9.配偶者控除
相続税の税制上の優遇措置として「配偶者の税額軽減」という制度があります。これは遺された配偶者の生活を守るため、遺産のうち配偶者が取得した部分については過重な税の負担をさせないという趣旨の制度です。
具体的には、配偶者が実際に取得した正味の遺産が、法定相続分以下であれば相続税は掛からず、法定相続分を超えても1億6千万円迄であれば相続税は掛からないというものです。これは、配偶者が取得した遺産は相続税計算から除外されるという意味ではなく、上記の相続税の計算で記載したように、全体の相続税を計算し、実際の取得価額に応じて税額を各人に案分した後、配偶者に案分された税額のうち、取得価額が法定相続分迄か1億6千万円迄の部分に対応する税額は納税を免除される、という意味です。従って、配偶者控除を適用することで、相続税の要納税額がゼロとなる場合であっても、適用しなければ税額が算出されるのであれば相続税の申告は必要になります。
また、相続税申告までに遺産分割協議が成立しない場合は、「未分割」の状態で申告することになりますが、配偶者控除が適用できるのは、「分割」されて、配偶者が実際に取得した財産のみとなります。(その後、遺産分割協議が調った場合には、修正申告及び更正の請求を行い、申告期限から3年以内であれば配偶者控除を適用することができます。申告期限から3年を経過する場合であっても、訴訟等のやむを得ない事情がある場合には、税務署に対して一定の申請手続を行うことで配偶者控除の適用が可能となります)。
配偶者が法定相続分、あるいは1億6千万円迄の全資産を取得して配偶者控除を最大限適用することにより、相続税の納税負担が大幅に軽減されるケースがありますが、特に配偶者自身も固有の財産を多く所有しているような場合には、将来の二次相続の相続税が高くなり、トータルで見ると不利になる場合もあります。このような場合には、どのような分割をすると一次相続、二次相続トータルで最も税金コストが有利になるかをシミュレーションして検討することが重要となります。
10.生命保険金及び退職手当金の非課税枠
生命保険の死亡保険金を受け取った場合、保険料の負担者が誰かに応じて課税関係は異なります。保険料の負担者が受取人自身である場合は、受け取った保険金は受取人の所得税(一時所得又は雑所得)の計算対象となります。負担者が受取人自身でも被保険者でもない場合は、その負担者から贈与を受けたことになり、贈与税の対象となります。そして、負担者が被保険者である場合には、「みなし相続財産」として相続税の対象となります(法的な相続財産ではないため、遺産分割協議の対象にはなりません)。負担者が複数である場合には、保険金がその負担割合に対応した各部分に案分されて、それぞれの課税の対象となります。
みなし相続財産となった生命保険金のうち、法定相続人が受け取った保険金については、「500万円×法定相続人の人数」迄の額は相続税が非課税となります。例えば、法定相続人が妻、長男、次男、の3名である場合、長男が600万円、次男が400万円の生命保険金(保険料は被相続人が負担)を受け取ったときは、非課税枠は「500万円×3人=1500万円」であるため、全額が非課税となり、相続税の計算対象の遺産に計上される額はゼロです。同じケースで、長男が1200万円、次男が800万円を受け取った場合は、合計2000万円の保険金であり、1500万円の非課税枠を超えているので、その超えている500万円が相続税の課税対象の遺産の額に計上されます。非課税枠は受け取った保険金の額に応じて案分され、長男は、1500万円×1200万円/2000万円=900万円の非課税枠。次男は、1500万円×800万円/2000万円=600万円の非課税枠、となります。従って、長男の取得した遺産は1200万円-900万円=300万円、次男の取得した遺産は、800万円-600万円=200万円、となります。
また、保険金を受け取ったのが法定相続人以外である場合には、その保険金に関しては非課税枠の適用はありません。
被相続人の死亡により取得する被相続人に支給されるべきであった退職手当金・功労金も「みなし相続財産」として相続税の課税対象となります。死亡後3年以内に支給額が確定したものがこの対象となり、そうでないものは相続人の一時所得として所得税が課税されます。この退職手当金等についても、生命保険金と同様に「500万円×法定相続人の人数」の非課税枠があります。
これらの非課税枠の計算に用いる法定相続人の数も、基礎控除の計算と同様に、養子の数の制限が適用されます。
11.不動産の評価
土地は、「一物一価」ではなく、俗に一物四価とも一物五価とも言われ、一つの土地に、複数の価格付けがされています。現実の売買取引の場面で成立する価格である「実勢価格」の他に、公的土地評価として「公示価格」、「路線価」、「固定資産税評価額」があります。
公示価格
国土交通省が主体となる「地価公示」と、都道府県が主体となる「地価調査」があり、ともに公正な取引の指標たる性格を有するものとして、各市区町村の一定の地域において土地形状、面積、利用状況等が標準的な土地を調査対象として選び、毎年発表されます(「地価公示」は1月1日現在の価格を3月中旬に、「地価調査」は7月1日現在の価格を9月中旬に発表しています)。この「公示価格」は概ね「実勢価格」の水準に近似していると言えます。
路線価
相続税や贈与税の計算上の基準とするために、国税庁が主体となり、毎年1月1日時点の価格が7月1日頃発表されます。「路線価」は「公示価格」の8割の水準に設定されます。
固定資産税評価額
各市町村が固定資産税を課税するための基礎となる価格として、「公示価格」の7割の水準を目安として設定されており、3年ごとに見直しされています。
上述のとおり、相続税申告上の土地の評価は「路線価」をベースとしたものになります。路線価に、間口の距離、奥行の距離、不整形な形状を加味して修正を行い、地積を乗じて評価額を算出します。都市部以外では路線価が付いていない地域(「倍率地域」といいます)もありますが、その場合は、固定資産税評価額に、「倍率表」に規定されている倍率を乗じて評価額を算出します。
このように土地(土地の地目としては、「宅地」「田」「畑」「山林」「原野」「雑種地」「公衆用道路」等がありますが、ここでは主に「宅地」の評価の説明をしています)の相続税評価額が算出されますが、これは「自用地」の評価額となります。「自用地」は、自宅敷地、駐車場、未利用の空き地、等が該当します。これらは、例えば売却等の処分をしようとする場合、他人の権利が関係していないため、特に制限を受けることがない土地であり、通常の評価となります。これに対して、地主として底地を他人に貸している場合(「貸宅地」といいます)や、貸アパートの敷地の場合(「貸家建付地」といいます)は、上に住んでいる人がいるために、立ち退き等をしてもらわない限り自由に処分等をすることができず、その意味で一定の制約がある、と言えます。相続税の評価では、このように権利に制約がある財産については一定の減額をすることになっています。
路線価図には「借地権割合」として、A~Gの記号が記載されています。A=90%、B=80%、C=70%、・・となっています。例えば、被相続人所有の土地が底地として他人に賃貸されていて、その土地が借地権割合が60%だとします。そして、路線価をベースに評価した「自用地評価額」が1億円であったとします。この場合、借地権の評価は1億円×60%で6000万円となり、被相続人所有の底地の相続税評価額は4000万円となります。
また、この土地が底地でなく、被相続人所有のアパートが上に建っているとすると、「貸家建付地」となり、その評価は
「自用地評価額」-(「自用地評価価額」×「借地権割合」×「借家権割合」×「賃貸割合」)
となります。
「借家権割合」は通常30%とされており、また「賃貸割合」はアパートが満室であれば100%です。
上の例で評価すると、
1億円-(1億円×60%×30%×100%)=8200万円となります。
「賃貸割合」については、例えば、一つの建物で自宅部分が半分、賃貸している部分が半分であれば50%となります。また、全部が賃貸アパートであっても、10室のうち1室が空室であれば90%となります。ただし、その空室が一時的なものであり、次の入居者を求めて募集活動をしているのであれば、空室として扱わなくてもいいことになっています。
建物の相続税評価は、固定資産税評価額で評価します。ただし、賃貸している建物(貸アパート、貸家等)は、固定資産税評価額の7割での評価となります。
よく相続税対策で賃貸アパートを建築する例がありますが、これは「自用地評価が貸家建付地評価になる」「新築アパートの建築費用に比べて固定資産税評価額は低い」「さらに、貸家のため、建物の相続税評価額は固定資産税評価額の7割になる」「(後述の)小規模宅地の評価減が適用できる」という節税効果を目的としたものと言えます。
12.小規模宅地の評価減
相続税の優遇措置の一つに小規模宅地の評価減(「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例)」という制度があります。東京等の都市部では地価が高く、自宅土地建物と預金が少しあるだけで相続税の納税が必要となり、自宅や事業用地を売却しないと納税できないような事態が生じかねないため、宅地の内、一定面積までの部分については評価を減額するという規定です。 対象となる土地は、相続人の「自宅の敷地」、「貸付(貸宅地、貸アパートの敷地、貸駐車場等)用の宅地」、「(貸付以外の)事業のための敷地」「同族会社の事業のための敷地」です。
自宅の敷地
330㎡迄の部分について、80%減額されて、2割の評価で済みます。
330㎡迄の部分について、とは、例えば自宅敷地が350㎡であれば330㎡分は20%の評価、超過する20㎡分は100%評価となる、という意味です。ただし誰が相続したか、で適用の可否が異なり、「配偶者」か、「同居親族」か、
「過去3年間借家住まいの親族(所謂"家なき子")」等が相続した場合に限り、適用が可能となります。このため、入口が別々の二世帯住宅においては「内部階段」を設けることにより、「同居している」という形態を整えるような相続税対策が良く用いられてきましたが、平成26年1月1日以降の相続からは二世帯住宅に関してそのような住宅構造の問題は関係なくなり、区分所有登記がなされていなければ同居として認められることとなりました。
また、被相続人が亡くなる前に老人ホームに入っていた場合、自宅についてこの特例が適用できるか否かについては、改正前は、「被相続人がいつでも生活できるように建物の維持管理が行われていたこと」や「老人ホームの終身利用権を取得していない」等の条件がありましたが、これも平成26年1月1日以降の相続からは「被相続人に介護が必要なため入所したものであること」、「その家屋が貸付等の用途に供されていないこと」という二つの要件さえ満たせば適用できることになり、要件が緩和されました。尚、上記の「家なき子」として80%の評価減を受けるためには、従来から①相続開始時点で被相続人には配偶者も同居相続人も居なかったこと②その宅地を取得する相続人等は相続開始前3年間借家住まいだった(自己又は自己の配偶者所有の家に住んでいない)こと③相続税申告期限迄は売却せずに所有してること という要件がありました。しかし、「家なき子」を満たすために、あえて自宅を売却して賃借に切り替えるような節税対策が横行したため、平成30年度税制改正により、平成30年4月1日以降(経過措置があるため実質的には令和2年4月1日以降)の相続からは、その宅地等を取得する相続人等が、③相続開始前3年以内に、三親等内の親族又は特別の関係のある一定の法人(同族会社)が所有する家屋に居住したことが無いこと ④相続開始前に居住している家屋を、過去に所有したことが無いこと という二つの要件が追加されました。
貸付用の宅地
200㎡迄の部分について、50%の評価減が適用できます。都心のタワーマンション等を購入して賃貸した場合、購入価格に比して相続税評価額がかなり低くなり、また、土地の持分面積が狭く単価が高いため、この貸付用の宅地としての50%評価減が有効に使え、節税対策として用いられることが多くなりました。しかし、相続直前に購入契約を交わす等、過度な節税対策が問題となったこともあり、平成30年4月1日以降の相続からは、相続開始前3年以内に貸付開始された宅地は評価減が出来ない、という規制が掛かることとなりました。ただし、相続開始前3年を超えて、事業的規模(一般的には、貸付の部屋数が概ね10室以上、または、貸付家屋がおおむね5棟以上という判定基準があります)で貸付事業を行っていた場合は規制の対象外です。また、平成30年4月1日前から貸付していた宅地も規制の対象外です。
貸付以外の事業用の宅地
400㎡迄の部分について80%の評価減が適用できます。
それぞれに、その事業等を引き継ぐ者が取得した場合等の条件があります。例えば、300㎡の貸宅地(底地)で、自用地としての評価額が3000万円、借地権割合が60%の場合、相続税評価額は、底地としての評価が1200万円、そのうち200㎡の部分については50%減額となるため、小規模宅地の評価減を適用すれば、最終的な評価は800万円となります。
小規模宅地の評価減は、どの土地について適用するかは納税者の自由であり、なるべく節税となるように選択して適用すべきです。組み合わせて適用することも可能であり、自宅敷地に165㎡分(330㎡迄という制限の50%)迄適用したとすると、利用率は50%であるため、貸付用の宅地に100㎡分(200㎡迄という制限の50%)適用する、ということも可能です(貸付用の宅地に小規模宅地等の特例を適用しない場合は、自宅敷地に330㎡まで、貸付以外の事業用宅地に400㎡まで、両方ともそれぞれフルに適用可能です)。小規模宅地の評価減を適用した宅地を取得した相続人は、その分相続税が節税できるため、どの宅地に適用するかは関係する相続人全員の合意の元に決定して申告することになります。また、小規模宅地の評価減を適用した結果、相続税がゼロとなる場合であっても、この特例の適用は申告が要件であるため、相続税の申告は必要になります。
13.非上場株式
非上場株式の相続税評価に関しては、その評価の方式として「純資産価額方式」、「類似業種比準価額方式」、「配当還元方式」があります。そして、相続した者が株を相続した後どのような株主になるか(「支配株主」か、「非支配株主」か)によって、また、会社自体の規模によって、それらの評価方式の適用の仕方が異なってきます。
純資産価額方式
会社の決算書の「貸借対照表」をベースに、一定の税務上の調整を加え、一株当たりの純資産価額を求めるものです。
類似業種比準価額方式
業種毎に上場企業の財務値と株価の関係の推移を国税庁が定期的に発表し、対象会社の財務値(配当、利益、純資産)実績をベースに該当する業種の株価から、対象会社の株価を算定する方式です。
配当還元方式
対象会社の最近の配当実績から、それを割り戻して一株当たりの評価を算出する方式です。
一般に、伝統があり過去の蓄積が多いような会社では「純資産価額方式」による株価が最も高くなり、また、配当はあまり行わずに内部留保に力点を置いているような会社であれば、「配当還元方式」による株価は非常に低くなります。
相続した株主が「非支配株主(典型的には議決権比率5%未満の株主で、有力株主グループの同族関係者でない等)」となるのであれば、株主として会社の意思決定に影響を与えることはできないため、その者の株の経済的価値は配当を受け取ることだけだと言えます。従って、その相続税評価額は「特例的評価方式」として、「配当還元方式」で計算してよいこととされています。
一方、相続した株主が「支配株主(有力株主グループの同族関係者等)」となるのであれば、「特例的評価方式」は適用することができず、「原則的評価方式」で評価することになります。「原則的評価方式」は、上記の「純資産価額方式」と「類似業種比準価額方式」を併用するような方式ですが、相続税法上の会社規模が大きいほど、一般的に低い評価となることが多い「類似業種比準価額方式」の比重が高まるようになっています。会社規模の判定は、「売上高」「総資産」「従業員数」で決まるため、例えば従業員数を少し増やすことで会社規模のランクを上げ、有利な方式での評価にするような相続税対策が行われる場合があります。
また、資産のうち、土地の占める割合が一定以上の会社(「土地保有特定会社」と言います)、株式の占める割合が一定以上の会社(「株式保有特定会社」と言います)等は、「特定の評価会社」とされ、純資産価額方式を中心とした特別の評価がされますので、注意が必要です。
14.延納及び物納
相続税は申告期限までに金銭で納付することが原則ですが、それが不可能であれば延納、物納が認められる場合があります。
延納
一時に金銭で納付することが困難な部分に対して適用されます。先ず、相続した預貯金だけでなく相続人自身の固有の預貯金を吐き出して、3か月分の生活費を残して納税をする必要があります。即ち現金、預貯金等、換価が容易な財産は納税に充てる必要があるのです。(ただし、例えば上場株式等はその対象ではなく、売却して納税する必要はありません)。そして、申請書提出等の手続を行うことにより、その不足分について延納が認められることになります。延納税額に見合う担保の提供が必要であり、利子税も掛かります。延納の期間は不動産の割合が多ければ、最長20年となります。
物納
延納によっても金銭で納付することができない場合に初めて認められます。物納可能な財産には順位があり、上位の順位の財産から物納しなければなりません。第1順位の最初のグループは、国債、地方債、不動産、船舶です。次は、不動産の中でも貸宅地等の劣後財産です。第2順位の最初のグループは、社債、株式、証券投資信託又は貸付信託の受益証券です。次は、株式の中でも事業休止会社の株式等の劣後財産です。第3順位が動産となります。
「物納不適格財産」とされるのは、「担保が付いている」「権利関係に争いがある」「境界が不明確な土地」「譲渡制限が付いている株式」「共有である株式」等です。従って、例えば土地の物納を考えている場合には、相続が開始してからでは遅く、事前に「借地権者の確定」「境界の確定」「賃貸借契約書の整備」「賃料の増額(あまりにも低いと不適格とされます)」等の準備をすることが大切です。
15.相続税納税資金の捻出
相続税の納税資金を捻出をするために、相続した土地を第三者に売却する場合があります。この場合、譲渡所得税が課税されますが、土地の取得費は被相続人の取得費を引き継ぎます。相続した土地の場合、古くからの土地で、取得価額が極めて低いか、取得価額が不明なことも少なくないでしょう。取得費が不明な場合、譲渡代金の5%を概算取得費として所得税の申告をすることになります。即ち、譲渡代金の95%が課税対象となってしまいます。土地の譲渡所得の税率は、短期(譲渡のあった年の1月1日における所有期間が5年以内のもの)では39%(所得税30%、住民税9%、復興特別所得税と合わせて39.63%)、長期では20%(所得税15%、住民税5%、復興特別所得税と合わせて20.315%)です。
相続した土地を相続税申告期限から3年以内に譲渡した場合は、その土地に係る相続税を譲渡所得の取得費に加算することができる、という特例がありますので、その特例を適用することで譲渡所得税を節減することができます。尚、土地の場合は譲渡した土地に係る相続税だけでなく、その者が相続した全ての土地に係る相続税を加算できるという特別に有利な規定がありましたが、平成27年1月1日以降に開始する相続により取得した土地に関しては、他の資産と同様、「譲渡した部分に係る相続税のみを加算することができる」ことに改正されました。
相続した財産の大半が同族会社の株式であって、優良な会社であるため相続税評価額が高く、納税資金の確保に苦慮する場合もあります。そのような場合には、会社の預貯金残高が多いのであれば、相続した株式を「自己株式」として会社自身に売却して、相続税の納税資金を確保する方法があります。非上場株式を第三者に譲渡する場合、売却益に対して20%の所得税等(復興特別所得税と合わせて20.315%)が課されます。しかし、非上場株式を自己株式として発行会社に譲渡する場合は、売却代金のうち、資本金等の額を超える部分は「みなし配当」として、譲渡所得ではなく配当所得として扱われます。配当所得は総合課税であるため、他の所得と合算されて、累進課税となります。所得が高額な場合は50%近い税率で課税されることになります。ところが、相続した株を相続税申告期限から3年以内に発行会社に譲渡する場合は、「みなし配当」ではなく通常の譲渡所得として扱われ、また、上述の取得費加算(掛かった相続税を譲渡所得の取得費に加算できる)の特例も使えるため、所得税を節減することができます。
16.相続税額の2割加算
相続・遺贈により財産を取得した者が、被相続人の一親等の血族及び配偶者のいずれでもない場合には、その者の相続税額にその税額の20%相当額を加算します。つまり、取得した者が、父母、配偶者、子である場合は2割加算はありませんが、それ以外は原則2割加算があります。養子であれば子として2割加算はありません。ただし、孫養子の場合は2割加算があります。孫が代襲相続人として取得した場合は2割加算はありません。
17.生前贈与と相続税
贈与には「暦年課税」と「相続時精算課税」の二つの方式があります。
暦年課税
その年の1月1日から12月31日迄の期間に贈与を受けた者が贈与を受けた額に応じて贈与税を課税されるものです。110万円の基礎控除があるため、年間110万円迄の贈与であれば贈与税は掛かりません。110万円を超過する部分に対して贈与税が課税されます。受贈者(贈与を受ける人)を中心に考えますので、例えばある人がその年に、Aさんから80万円、Bさんから50万円の贈与を受けたとすると、その人は合計130万円の贈与を受けたことになり、110万円を超過する20万円に対して贈与税が課税されます。
相続時精算課税
贈与の年の1月1日現在60歳以上である父母又は祖父母から20歳以上である子又は孫に対して行う贈与で、この制度で贈与をする旨の届出書等を添付して贈与税の申告を行うことにより適用することができます。この制度で贈与する場合には、2500万円が非課税となり、それを超える部分に対して20%の税率の贈与税が課税されます。この制度を一旦選択すると、その後は、その贈与者からの贈与は「暦年課税」で贈与を受けることはできません。(贈与者毎に選択でき、父からの贈与は「相続時精算課税」で受けて、母からの贈与は「暦年課税」で受けることは可能です)。この制度での贈与金額は累積額で管理され、通算で2500万円を超えるとそれ以降の部分に対して20%の贈与税が課税されることになります。
また、「相続時精算課税」という文字通りに、贈与された財産は、相続時に相続財産に持ち戻されて、相続財産に加算されて相続税の計算が行われます。そして、既に納付した贈与税については、計算された相続税から控除してもらえます。財産の評価額は贈与した時点の評価額で固定されるため、例えば長期的に上昇して行くことが予想される同族会社の株式等を「相続時精算課税」で贈与すれば、将来の高くなった時の評価ではなく、贈与時の低い価格で固定することが可能になります。(ただし、将来価格が今よりも下落する場合には反対に不利になります)。
「暦年贈与」の場合でも、相続・遺贈により財産を取得(みなし相続財産となる生命保険金等の取得も含みます)した者が、その相続開始前3年以内にその相続に係る被相続人から贈与を受けていた場合、その贈与財産の評価額は相続財産に加えて相続税を計算し、既に納付済の贈与税は相続税から控除されます。ただし納付した贈与税額の方が相続税額より多い場合にも超過額が還付されることはありません。
婚姻期間が20年以上である配偶者から居住用不動産又はその取得用資金の贈与を受けた場合は、財産価額が2000万円迄(基礎控除と合わせると2110万円迄)贈与税が非課税となります(「贈与税の配偶者控除」といいます)。この特例を使用して贈与した場合は、仮にその贈与が贈与者の相続開始前3年以内の贈与であったとしても、その控除部分の金額は相続税の計算に加算する必要はありません。
18.名義預金
相続税申告で最も問題となるのは「名義預金」の問題です。税務調査においても最も重点的に調査される項目と言えます。「名義預金」とは、預貯金の口座名義自体は例えば子供や孫のものだけれども、実質的には親のものであり、相続財産を構成するものです。「名義預金」となるのは、典型的には、名義は子供になっているけれどもその存在を子供が知らず、通帳も銀行印も親が管理しているようなケースです。このようなケースでは子供の財産というのは名ばかりであって、実質的には親の財産とみなされる恐れが多分にあります。昔子供に贈与をしたものだ、と抗弁したとしても、贈与は贈与者と受贈者の双方の合意に基づいて成立するため、子が知らないような場合は贈与自体も成立しておらず、親が勝手に子供名義の口座を作っただけだ、とされてしまいます。子供の財産に確実に移すためには、例えば、暦年贈与を利用して、年間110万円の範囲内で、少しずつ贈与を行うことが考えられます。きちんと贈与契約書を作成して、贈与として子供の口座に送金する(それを証明するために贈与契約書に公証役場の確定日付を取る、等の、より確実な方法もあります)ことで、名義預金として否認されることはなくなります。
特に注意が必要なのは、妻が主婦の場合です。妻の名義で多額の預貯金残高がある場合、名義預金として実質上はご主人の財産ではないか、と疑われる可能性が高くなります。主婦であれば、そのような多額の預貯金を形成する収入がないはずなので、妻自身が親の相続で取得したとか、結婚する前にしていた仕事で多額の預貯金があった、等の合理的な理由が無い限り、名義預金とされる恐れが高いといえます。
19.配偶者居住権
令和2年4月1日以降の相続から、配偶者居住権という権利が創設されました。従来は、例えば相続人が妻と長男の二人で(それぞれ法定相続分は2分の1ずつ)、遺産の大半が自宅不動産であるような場合、妻が自宅に住み続ける権利を確保しようとして自宅不動産を相続してしまうと、それだけで妻の法定相続分を超える財産を取得してしまうことになるため、妻は預貯金は全く相続できないばかりか、むしろ代償金を払わざるを得ないようなケースすらあり、配偶者の老後の生活基盤の確保が問題となっていました。そこで、自宅不動産自体は相続しないけれども、そこに住み続けることができる権利として、配偶者居住権が創設されました。遺産分割協議書又は遺言で配偶者居住権を定め、登記することによりその権利が保護されます。配偶者居住権を設定した場合、建物、土地のそれぞれの相続税評価額の一部が、配偶者居住権の価額(建物部分)と敷地利用権の価額(土地部分)となり、全体からそれらを控除した価額が、土地、建物を取得した相続人(例えば長男)の取得した財産の評価額になります。つまり、配偶者居住権を設定しても、全体の相続税評価額は変動しません。配偶者居住権の評価は、例えば次のようになります。
・遺産分割時の配偶者の年齢が80歳(女性)なら、平均余命は12年。
・残存年数12年の「複利現価率」は、0.701(法定利率3%の場合)
(⇒12年後に貰う100万円の価値は、今貰う70.1万円と同じ、という意味)
・建物の法定耐用年数=33年(木造建物の場合)
・建物の経過年数=10年
・建物の残存年数=23年(←33年-10年)
このようなケースで、建物の相続税評価額が1,000万円であるとすると、
配偶者居住権=1,000万円-1,000万円×(23年-12年)/23年×0.701=664.7万円となります。
また、土地の相続税評価額が2,000万円であるとすると、
敷地利用権=2,000万円-2,000万円×0.701=598万円となります。
土地、建物の所有権を取得した子の相続税評価額は、
建物=1,000万円-664.7万円=335.3万円
土地=2,000万円-598万円=1,402万円となります。
配偶者居住権を設定したその配偶者が将来死亡した場合、配偶者居住権は法律上消滅し、二次相続における課税対象となりません。そのため、配偶者居住権を設定することで、二次相続迄含めたトータルの相続税が節税できる場合があります。ただし、トータルの税額は、小規模宅地等の特例の適用の可否、配偶者の税額軽減の適用の効果等、複雑な要素が絡むため、配偶者居住権を設定することでかえって税額が増える場合もあり、必ずしも節税とはならないことに注意が必要です。